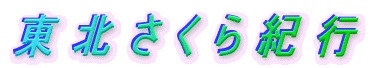 2006/5/2�`5/4  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �� �� �� ���k�n���͍s�������Ƃ̂Ȃ��Ƃ���ł���B ��������S�[���f���E�C�[�N�ɓ��k�̂����猩�ɍs���Ȃ��H�ƗU�����������B ��u�A�l�o�̑��������͔��������Ȃ��Ǝv�����B�����s���Ȃ��Ƃ����͂��͂Ȃ��ƌ��z���Ă���B���������A���k�n���͂��̎��������̌����Ȃ̂�Ƃ����B���k�ƕ����Ċp�قɍs�������ƃ��N�G�X�g�����B ���ƈꏏ�̗��́A���������܂ŏo�����č������Ă���o������B�O�㔑����Ɠ����ݏZ�̎q���B�Ɖ��B���p�قɍs������A�V���b�s���O������A���ɐH�����ł���B���i�͗���ĕ�炵�Ă���̂Ō�炢���ꂵ���ЂƎ��ł���B���܂��t�����s�̂悤�Ɏv���Ă���B �y���@�@���z
�P�D�@�����`�p�� 5��2���i�j�E�E�E�����w���d�F�k���F8��25���W�� �������� ���]�[�g���炩�ݍ��ɏ�� �O �O��p �٥�� �X ���@�݂��̂����o�I�s3�����̗��̎n�܂�ł���B ����͗��s�Ђ̃c�A�[�i�Y����t���j�ɎQ������B ���̂킯�́A �����k�̂�����̓S�[���f���E�C�[�N�̍��������ł��邱�ƁB �����G���ł���B�R���p�N�g�Ɍ����悭���肽���B ����2�l�Ƃ�3�l���ŁA����������k�͏��߂Ăł���B ���̊�]�Ƃ��Ċp�قɍs�������Ɠ`�����B ����ȏ����ɍ��v�����R�[�X�Ŏ�������z���Ă��ꂽ�B �W�܂��Ă݂�ƎQ���҂�15�l�A�\�z��菭�Ȃ��B �ꖺ�̑g�ݍ��킹�͎���������ŁA���Ƃ͂�����������N�̕v�w����ł���B ���N��GW�͋x�݂������C�O�E�o�g�������B��҂͍���̗���炢�ŋߏ�̃A�W�A�֏o�������̂�������Ȃ��B�����猩�������낢��ȃR�[�X������I�������������ƂȂǂ����R�ł��낤�B �ȑO�͓��k�����̗�Ԃ͏�씭�̃C���[�W���������B���k�V�����ɂ͏��߂ď��B�H�c�s���̢���܂��X����͒荏��8��56���Ɋ���悤�ɂ��ē����w�Ԃ����B �ԑ�����̌i�F�͕��삪�L����A�ӂ�ɎR�������Ȃ��B�֓�����͍L��ł���B 2�N�O�ɊJ�ʂ�����B�V�����E�������̐V����Ƃ͑�Ⴂ�ł���B������̓g���l������ł���B�Ԗ��͢�ߣ�����A�Èł𑖂������̂悤�ł���B�ԑ̂͐V�����̂ŏ��S�n�͂悢�B ��Ԓn�͏��A��{�A���A�����A�c��A�p�فi���ԁj�ł���B �p�ق܂Ŗ�3���Ԃ̏�Ԃł���B��Ԃł̗��͋v���Ԃ�ł���B�ԑ����牓�i�߂��A�ԓ��̋�Ԃ������Ċ�����̂��悢�B ���Œ��H�̉Ԍ��ٓ����ςݍ��܂ꂽ�B�s���̓s����A���Ԃ���܂ł̎ԓ��ŐH�ׂ�悤�ɂƂ������ƂŒ����L�����B�W���ʂ�̉Ԍ��ٓ��ł���B����̍���ŗD�������t���ł���B�������Ԍ��ٓ��A�`���i�����`������Ă���B ���Ă��ʎq�A�I�̏Ƃ�Ă��A�{�������c�g���A�C�V��F�c�q�A �Ԃ��傤�A�̉Ԃ̘a�����A�g�ԕ�ݏ����A�������킹�A �N�t�����A�������X�A�t�̐�����сA���̕��B �� ��������Ìy�قŁu�ӂ��̂Ƃ��v�������B �����ŘA�����Ă����X�s���́u�͂�āv�ƕ��������B �S�Ȃ�����Ԃ̃X�s�[�h�������Ă����悤�Ɋ������B�������߂��A�c��Εӂ�ɗ���Ɛ��H�̘H���Ɏc�Ⴊ�ڂɕt���悤�ɂȂ��Ă����B�R�ɂ��c�Ⴊ�E�E�E 12��12���F�p�ىw�� �Q�D�@�p�@�فi�H�c���j�@ �p�ق̉w�͏�����܂�Ƃ��Ă���B ��������o�X�ňړ�����B�ό��o�X�͍O�O���痈�Ă����B���������Ԃɏ���ԈȊO�͂��̃o�X�ňړ����邱�ƂɂȂ�B �ŏI��3���ځA���ˉw����V�����ɏ���ē����֏o������܂ł̋�ԂɂȂ�B 
����̗��ŁA�s���Ă݂����A�O�������Ȃ������A�p�ق̒��ƍ��ł������B ���̗��͂����猩������ړI�ł���B�p�ق̕��Ɖ��~�����P�������������w����Ƃ���ł���B �g�݂��̂��̏����s�h�ƌĂ��p�ق́A�鉺�̒�����A���Ɖ��~�̎p���ł��悭�c���������Ƃ�����B�����̑������Ɖ��~�ɁA�鉺���̖ʉe���F�Z���Y�������݂ł���B��╻�͎c���Ă��Ă��A�����܂Ŏc���Ă���鉺���͂������Ȃ��B ������̖����Ƃ��Ă��m���Ă���B ���͎O�����R�Ɉ͂܂�A��͐�k����ɊJ���Ă���n�`�ŁA�鉺�����`������̂ɓK�����ꏊ�ł������B���̒����̉Ώ����L��i�h�Βn�сj�����ɖk�ɓ����i���ƒ��j�A��ɊO���i���l���j������Ă���B��k�Q�L���͈̔͂ɏW�����Ă���B �k���́g�����h�͕��Ɖ��~�Ő[���ؗ��ŕ����āA�����Ƃ�Ɨ��������̂��邽�����܂��B��́g�O���h�͏��Ƃ��т����薄�߂Ă��銈�C�̂��钬���݁B�َ��ȋ�Ԃ��ΏƓI�ł���B �փ����̐킢��A�p�ٗ̎�ƂȂ��������`�������a�U�N�i1620�N�j�ɒ��Â�����J�n�����B �����ƒf���͋��s�̌����o�g�E���|�`�ׂ��p�ق�̗L���A�傢�ɋ��������������ꂽ�B �����ɋ��̂���������p�قɈڐA�����̂ŁA���݁A�L�X�Ƃ������Ɖ��~�̒�ɂ͎���200�N�ȏ�̋���Ȏ}������������A�J�Ԋ��ɂ͕O�ؓ���i�Ђ̂��Ȃ�����j��̃\���C���V�m�Ɣ������������B �d������蕥���A�������L���A�]�ˎ���̕��͋C�����̂܂ܓ`���镐�Ɖ��~�Q�́A���a51�N�i1976�N�j�u�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肳�ꂽ�B ���a�U�N�i1620�j�H�c�˂̎x�˂Ƃ��ď鉺�����`�������B�ȗ�380�N�A���̌`���͑傫���ς���Ă��炸�A�������j�̐����Ă��钬�ł�����B ���Ɖ��~�����w�ł���Ƃ��낪�����i�L���Ɩ���������j�B �U�����c��A��т͍��̏d�v�`���I�������Q�ۑ��n��ɑI�肳��Ă���B�U�O�O���̕��Ɖ��~�ʂ�ɂ͒�����A����A�������Â��B �y�p �� �� �j ���E�� �� �Ɓz �����������鎞�Ԃ��Ȃ������̂ŃK�C�h���E�߂̐��Ɓi�L��500�~�j�����w�����B �p�ٗ��j���E���Ƃ͊p�ق��\���镐�Ɖ��~�i�����̐���204�őg�����������j�ŁA���h�Ȗ��傪�ڈ�B �ڈ�̖�����B�낤�Ǝv�������ό��q���Q��āA�܂Ƃ��ɎB��Ȃ��A�߂������ƁE�E�E ���ɓ���ƁA�L��ȕ~�n�Ɋ��������̕ꉮ�A���푠�A���ɑ��Ȃǂ��c��A�]�ˎ���̎j���Ȃǂ�W������~�j�~���[�W�A���A�H�c���y�فA���Ɠ���قȂǂ�����B 
�����ŏH�c���悪���邱�Ƃ�m�����B �H�c�͍]�˂��牓�����B�ɂ���Ȃ���A�����𗬂͕Ӌ��̒n�ł͂Ȃ������B ����k�O�D�̑��݂ł���B ���˓��C�E���{�C���o�ĉ��B�̒n�֏���������^�Ԗk�O�D�́A���Ƃ��Ē��肩�狞�֑���ꂽ��̕i�X���������H�c�̒n�ւƉ^�̂ł���B ���Ƃ̊W���Z���v�ۓc�ˁA�p�َx�˂͐ϋɓI�ɏ�����������A�ˑS�̂���������ɐZ��@��Ɍb�܂�Ă����B �܂����ꌹ���̗��w�Ƃ̊ւ�������B ���w�����ɕ`���ꂽ�ڍׂȑ}���G�́A���̐��m���Ől�X�����Q�������B ���w�̑n�n�҂ł��镽�ꌹ���͗m��̌��������Ă����B �v�ۓc�ˎ�E���|�`�ցi�悵���j�͍]�˔˓@�Ő��܂�A�]�˕������{��g�ɂ��Ă����B��ɏH�c����̒S����ƂȂ����B �p�ق̒n�ɐ��܂ꂽ���c�쒼���́A�N��������˂����A15�ŋv�ۓc�˂̌�p�G�t������h�̉�@���w�B�����G��@�A�Ԕh��@�A�����@���A��X�̉敗���w�B 
���ꌹ�����ˎ�ɏ����ꂽ���A�����͏o������B �������琼�m��̉A�e�@�E���Ö@��������ꂽ�B �������狳�����ꂽ�m��Z�@�́A���c�쒼����ʂ��ėm����u���p�ُ��E���|�`�Z��ˎm�E�c�㒉�����W�܂�A�H�c���旲���̊�b���z���ꂽ�B �R�N�ԁA�]�˂̌����̉��ŗm����w�����́A���c�������u��̐V���v�̐}�ł�`�����B �������̓��{�ŁA�������]�˂��牓�����ꂽ���k�̒n�ŁA�ԊJ�����H�c����̐��E�͒�����܁i���N32���j�ŒZ���J�Ԋ����I�����B ���c�쒼�����\���G�Ɛ}�ł�`�������ł́u��̐V���v�͒뉀���u�n�C�J���فv�ɓW������Ă���B �~�n���ɏ��c�쒼���̋����������Ă���B�ނ̐��Ƃ����̋߂��ɂ������Ƃ����B �����߂��̃p�l���ɂ́A���c�쒼���̈ꐶ���킩��₷����������Ă���B�ǂ݂Ȃ��珉�߂Ēm�邱�Ƃ����������ł������B�@�@ �p�ق́A�鉺�̒�����A���Ɖ��~�̎p���ł��悭�c���������Ƃ�����B��╻�͎c���Ă��Ă��A�����܂Ŏc���Ă���鉺���͂������Ȃ��B
�R�D�@�p�@�فi�H�c���j�A �`���Ɖ��~�ʂ�̂�������` ���Ƃ̌��w������A���R�U��A�����猩���ł���B �鉺���̖ʉe���c�����Ɖ��~��т͂�������������ł���B����200�N���z����Ö�����ؗ�Ȃ������܂��ł���B�ʂ��������������Ă���l�������B ���͖��J�Ŋό��q�������B�l�͎Ԃɏ���ėD��ɂ���������łĂ���q��������B����̂���i�ςł���B�����A��������A�l�͎Ԃ́A������̕��i�ɂ��܂��n�������Ă���B ��������͏����̕��ŗh���B�Ȃ�Ƃ������ʏ���镗��ł���B�ύ��q���Ђ�����Ȃ��ɐ��ꉺ�������}�z���Ɏʐ^���B���Ă���B�ԂɈ������Ă��F������l�ɉf���Ă���B �ʂ�ɍ���H�Z���^�[�A���ԕ����A���H�̓y�Y�����A���X�g�����������ԁB ���̔�H���i�i�����A�~�A�z�j�������A�Z���^�[�ł͎��肵�Ă��������ʂ�����ꂽ�B ��̖͗l���ω��ɕx��ŕ\�ʂ͉�������B�y�Y�ɌC�ׂ�����߂��B �����������Ԃ��~�����B�������茩�������A����ꂽ���Ԙg���ł͎d�����Ȃ��B�����ꃖ���̍��̖����A�O�ؓ���͔̉Ȃֈړ������B
�`�O�ؓ���i�Ђ̂��Ȃ�����j�͔̉Ȃ̃\���C���V�m�` ������̓\���C���V�m�ł���B�������ŗ��݂ɂт�����炫����Ă���B���F�̑я��悵�Ă���B�y�������Ɨ����̍����d�Ȃ�g���l���ƂȂ��Ă���B�����ƕӂ���ς��Ɩ��邭�Ƃ炷�B�Ԃ��������Ă���̂Ŏ����E�ʊ�������B �͐�~�ł͉����n�܂��Ă���B ���̌�o�X�͏H�c�s�����������B�@ �S�D�@�H�@�c�@�@ ��Ԃ��Ă���o�X�͍O�O����z�Ԃ���Ă���B �K�C�h������O�O�o�g�ŕ��i�͒Ìy�ق��a���Ă���Ƙb���B����ł������͕W����ɋ߂����t�Řb���Ă����Ƃ����B���ǂ��a��̌������o�邪�A�Ђт��͗D�����B�ԓ��ɓ��k�̒n�}���\���Ă���B�������Ȃ��猾�t���a���Ă������a���ĂȂ�����˂Ɩʔ����B ���̗��̑S�s���̃A�E�g���C�������B���j�[�N�ȃ��[�g�ł���B �H�c���ƐX����ʉ߂���B�����̓��{�C���Ɠ����̓������łQ��ɂ킽���ė������܂������ƂɂȂ�B���{�C���ł͌ܔ\���ɏ�Ԃ���B����̊y���݂̈�ł���B �ፑ�̕�炵���������B �S������P�O���܂ł��ό��V�[�Y���ł���B�~���̓X�L�[�q�ȊO�K���l�͖w�ǂȂ��B �����E�H�c�Ԃ̍����S�U�����͐��Ⴋ�悯�̖h��@���ݒu���Ă���B�M���@�͏c�^�������B�Ⴊ�����Ɨ������邩��A���������ƐႪ�ς���B�Ȃ�قǁE�E�E�[���B �`��H�����̂�����` ��H�����͏H�c�s�̒��S���ɂ���A�����Ă̏H�c�ˎ卲�|���Q�O�����z�����v�ۓc��ՁB �Ί_��V��t���Ȃ��y�ۂ̂��镽�R��Ƃ��Ēm����B �����͂P�W�X�U�N�����ƁE���������ɂ����{�뉀�Ƃ��Đv����A���w�ҁE���ǒm�ɂ�薽�����ꂽ�B���{�̓s�s����100�I�ɓ����Ă���B �����ɂ�800�{���z���\���C���V�m�������ɍ炫�����B������܂���Ԃ̓��C�g�A�b�v�������B�ɂ������ƂɂS���R�O���ŏI����Ă����B�P���ԗ]�艀���̂���������ĉ�����B�S���E�̂Ȃ��ɂ����炪�L����B����̋�𔖓��F�ɂق�̂�Ɛ��߂�B�����O�ɂ�����������Ղ蒭�߂邱�Ƃ��o�����B��͂�����艷��ɐZ���荡���̔���������Ƃɂ��܂��傤�B �v�ۓc��\�� ���d�Ȏ����ł߂Ă����{�ۂ̐���ŁA�ؑ��Q�K���Ċ����̘E(�₮��)��B�G�}�┭�@�������������ƂɍČ������B �������ɂ͍��|�����فA�H�c�s���}���ٖ����ق́u�ΐ�B�O�L�O����A���쐭�g���p��(���c�k���̍�i������)�����w�������Ƃ���ł������B�����珄�肪��ړI�̃X�P�W���[���ł͖����ł������B����͖K�˂����B
�T�D�@�H�@�c�@�A �����̔��܂�͏H�c�s�x�O�ɍ݂颏H�c���Ƃݣ�ł���B 300�̑嗁���140�̘I�V���C���y���߂�L�X�Ƃ�������h�ł���B �����̑�����A���𗬂�鈮��A���݂ɂ͒W�����F������̒��ɉ��ނ悤�ɉf��B �[�H���Ԃ܂ŊԂ��������̂ő嗁��}�����B�傫�ȘI�V���C��2��������B���{�뉀�߂Ȃ��瓒���̒��ɐg�߂�ƐZ��Ɨ��̔���������ԁB�D�����S�n�悳���S�g���݂��ށB �S�g���u���ׂ��ׂ̖��v�ŕ���ꂽ�悤�Ȋ��G������B �͊���_�d���H����B �������X�A���ׂ��ׂɂȂ颔��l�̓���A �ۂ��ۂ��̉����肪�������颂������܂�̓���Ƃ��Đe���܂�Ă���Ɛ�`���Ă���B �����ɐl�C�̏h�ł���炵���B �[�H�̓O�������(���{�C�̑N���E�R�E���`�E���肽��ۓ�)�ƂȂ��Ă���A���҂ł������ł���B �L�ԂɉƑ����Ƃɍ��r�t���V�����ׂĂ���B �A���R�[���ʖډƑ��ł���B���肾���ł��ƁA�������͏H�c�̖������������������̗���A���͔��̃O���X���C���Ŋ��t�����B �k�̐H�ו��ɂ͒������Ɠ�������B ���V�̏��ڂŒǂ����B ��O�ɢ����㣂��Y���Ă���B�ǂ�ł݂�B �u�{���̓O�����v�����̃R�[�X�����I�т��������܂��āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B���͑����m�̊C���ɎY���������A�炿�܂����B����8�ł������܂��B���x�H�ׂ��납�Ƒ����܂��B �����̂悤�ɑ�ϐ�������낵���̂ŁA���S���ĐH���Ă��������܂����A���̂ق�����ς�낵�����Ǝv���܂��B1���͂�����ɁA����1���͏Ă��̂���낵�����Ǝv���܂��B�����̕��ɂ̓O���^���������߂̈�i�ł������܂��B �ł��邾�����������ɂ��H�ׂ��������āA���c�����ɐH�ׂĂ���������Ύ����{�]�ł������܂��B�v ����͈ɐ�����2���g���Ă��郁�j���[�ł���B 1���͕Аg���O���^���ɂ���2���������Ă���B��������͌�ʼn^�ꂽ�B ���͍��ƎR���{�̃V�[�Y���ł���B�������g���C���[�W���������͒������A���ꂵ���B �Ƃ�킯�H�c�́u���`�E�������v�u���肽��ۓ磂ɒ��ڂ����B �ڂɏĂ��t���f�W�J���Ɏ��߂��B �ɐ����т̑���Ƃ͕ʂɋ��̎h�g������B���܂���̒��Ɏh�g��������B�G��Ɨ₽���B�ЂƖڂŏH�c�Ƃ킩��A�C�f�B�A�ł���B �u���`�E�������v ���w�u�H�c�����v�ɂ��S���Ă���n�^�n�^���g���Ă������d���̗����B��x�͖{��ŐH�ׂĂ݂����Ǝv���Ă����B�����ŁA�n�^�n�^�́u�ށv�Ə����B ��������d���Ă��A��蕪���ĔM�X���^��Ă����B �n�^�n�^�A�����A������Ȃǂ������Ă���B�X�[�v�̐F�͑���̂Ȃ������F�B�����ł��邱�Ƃ�������B�L�݂̂Ȃ��A�|���̂��锖���A��i�Ȗ��킢�ł���B�`���Ƃ��ꂢ�ɒ������B �u���肽��ۓ� �H�c���y�����̑�\�i�́A���肽��ۓ���y���݂ɂ��Ă����B ���Ƃ��ƁC�u���肽��ہv�͏H�c���k���̗t�u�}�^�M�v�̗����ł������ƌ����Ă���B ����{�A���肽��ہA��ؗނ��ύ���ł���B�X�[�v�̏o���͔���{����Ƃ��Ă���B 30�N�O�A���߂Ă��肽��ۂ�H�ׂĈȗ���D���ɂȂ��Ă���B�������A��̎������ł͌������Ȃ��B�Ⓚ���͍D���ɂȂ�Ȃ��B�v���Ԃ�Ƀz�N�z�N�Ƃ����H���̂��肽��ۂ�H�ׂ��B�Ăǂ���H�c�Ȃ�ł̖͂��ł���B�X�[�v�������������ł��������B ���̒��`����i�ł���B �a�H�͏o�������ł���B�ǂ̗���������o�������J�Ɏ���Ă��邱�Ƃ��M����B �k�̗����͒������B�ڂɏĂ����A��Ŋo���悤�Ɨ~�����Ē������B �x�ޑO�ɂ�����x�A�I�V���C�ɐZ�������B�������Ȃ��畗��̂����i�ł���B �u�������v �@���݁u�������v�͖{���u�n�^�n�^�v�������Ƃ������m�ł��邪�A���l�ɂ�錴���i�n �^�n�^�j�̌�������A�ߔN�ł͂������菭�Ȃ��Ȃ�A�u���킵�v��u�R�E�i�S�v�Ȃǂ̑�ւ������ɂȂ��Ă���Ƃ����B�F�������A�n�^�n�^�����g�̋��ł��邩��ɈႢ�Ȃ��B����́u������v���@���݂���������͒��F�ɐF�Â��Ă���B
�U�D�@�@�X�@�@ �Q���ڂ̒��ł���B�W���S�O���A��H�c���Ƃݣ���o������B �����̍s���͒����B�h�ɂ��钅���X�P�W���[���ł���B(����) �H�c�s���o�����ē��{�C�����ɖk�サ�ĐX���ɓ���B��ɂ͓����̓����n�����z�����čĂяH�c���֕����߂邱�ƂɂȂ�B ������Ԃ̌����A���_�R�n��ڎw���ăo�X�͑���B�قړ��{�C�����ɖk�シ��̂ŊC���Ղ߂�B���鏊�ɓ~�̖\���Ꮬ����������B���������B�H�c���̓W�����T�C�̎Y�n�ł���B�[�H�̋z������A�������ɂ��g���Ă������B ��H�c�������X�ށX�i�n�^�n�^)�@�j���Œj���u���R�@�\��t�c�O�R�[���E�E�E� �ƏH�c�����ɂ��S���Ă��锪�X��ʉ߂����B�₪�ĐX���ł���B �y�� �_ �R �n (���E���R��Y)�z ���_�R�n�́A�X�����암�ƏH�c���k�����ɂ܂�����A��P�R���w�N�^�[���̎R�x�n�тł���B���E�ł��ő勉�̃u�i�����т��L���������̋M�d�Ȏ��R�ł���B��17000�w�N�^�[�������E���R��Y�̓o�^�n��B ���̓V�R�L�O���̃N�}�Q����C�k���V�A�j�z���J���V�J�Ȃǂ��������Ă���B2000��̍����A���_�R�n�ɍ炭�A�I�����}���e�}�ȂNjM�d�ȑ��Ԃ���������A���A���̊y���B �X���̏\�����̃��[�g�Ŕ��_�R�n�ɓ����Ă������B �����R��1230���[�g���A�u�i�̖������B �K�C�h�\�\��u�i�͊����ŏ����ƁH� ���q�\�\��ؕтɖ�� �K�C�h�\�\��u�i�͐����������؍ނɂȂ�Ȃ��B���̂Ƃ��艽�ɂ��Ȃ�Ȃ�������?�Ə����̂� �{���̂悤�Șb�ɏ�q�����Ă���B �u�E��𒍖ڂ��Ă��������B���{�L���j�I���������Ă��܂��B�v �͂��߉��̂��Ƃ���������Ȃ������B���������R���������Ă����B�o�X��̖ڐ�����ł͒��ӂ��Č��Ă��Ȃ��ƌ��߂����Ă��܂������ɂ�����Ƃ����ł���B�����S�c�S�c�����┧���Ƃ����B �傰������Ȃ��H�@���炪���������ȁH ���̖��̗R���́A����Ȕ����┧���A�����J�E�R�����h�����̃O�����h�L���j�I�����v�킹��Ƃ��납��B
�y�\ �� �� (�Ìy�������)�z ���ړ��Ă̏\��A�����̃n�C���C�g�̐r�ɍs�����߂Ƀo�X���~�肽�B�Ȃ��炩�ȎR����o���Ă����B �\��́A33�̌Ώ��Q����Ȃ�u�i�̐X�Ɉ͂܂ꂽ�����������ł���B���ł��r�͏\����\���閼�ł���B ���X33���������A���i������j�R������āA�ǂ��~�߂Ă��܂����B ���R�̒��ォ�璭�߂�ƁA�������r�͐X�̒��ɉB��A�傫�Ȓr������12���������Ƃ���u�\��v�Ƃ�����悤�ɂȂ����B �����t�݂��߂Ȃ�������Ă����ƍ���Ɍ������Ă���B�q�����Ă���������Đ��͐����ɂ����B�Ō�ɂ�����Ə�����Ƃ���ɐr�̕\�����o�Ă����B �y�@�r�z �u�����I�v ���̐F�������r�[�A�����킸����ۂB ���t�ŕ\���ł��Ȃ��F�ł���B�S�̒��܂Ő��ݍ���ł���悤�Ȑ[���F�����ł���B �C���N�𗬂����悤�ɐ^���Ȍΐ���X���Ă���B���̐F�͐_��I�ŁA�Β�ɂ̓u�i�̖��Â��ɉ������A���z�̌��ɂ���Ēr�̐����ω�����B �r�͔��_�R�n�̐����̎R���Ƀ|�c���Ɗۂ��J���ꂽ���a�S�Tm�A�[���Xm�̍��ɂȐ����̗N���o���r�ł���B���̐��̓������͐_��I�ŁA�̂���L���ł���B���̐F�͔��_�R�n���L�̐����F���鐅�̕��q�̐����ɂ��A�������R�̐F�ł���B �Î�̓m�̒��ŁA�����ƌ��Ă���ƁA�z�����܂ꂻ���Ȃقǔ������_��I�Ȉ�ۂ�^���Ă����B�d�����ɂ���������B�Β�܂Ō��������ȓ����x�A�ؘR�������˂��z�������˂��ČΖʂ̓L���L���ƌ����Ă���B �r�̎�O�ɂ��镦��(�킫��)�̒r���f���炵���B �r�̒ꂩ�炱��Ɣ��_�R�n�̕��������N���o���Ă���B�������̂��������X���Ă���A�r�ƕ���ŏ\����w�̐_��I�Ȕ������ł���B���ӂ̃u�i��~�Y�i���̌ÖƂ̌i�ς��G�ɂȂ�B �����o�R���̊K�i��������Ƃ���ŁA���E�����邭�J�����B�u�i�̌����т��L�����Ă���B�X�e�b�v�ɂ͊���Ȃ��悤�Ƀ`�b�v�ނ��~���Ă���B �u�i�̎��R�тŁA�Ⴂ����V�܂Ő������Ă���B���s�V�̂悢�ؗ��ł͂Ȃ���������̐X�������B���傫���L���Đ[�ċz�����B�厩�R����̃v���[���g�A����C�����������I�I ���蓹�A���������ʼn��炵���ӂ��̂Ƃ��������B�������ł͎����̂��̂͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��B �y�T���^�����h���_�z ���H�̓T���^�����h���_�Őۂ����B �T���^�����h���_�Ƃ͂Ȃ낤�H�Ǝv�����B ���E���R��Y�ł��锒�_�R�n�̎��E���_�x�̘[�Ɉʒu���A�N���X�}�X�̃��[�h����N��ʂ��Ċ������閲�����ς��̃T���^�N���[�X���[���h�ł���B
�������t�B�������h���A���i���̔�����Ă���B�t�B�������h�������Ă����T���^�N���[�X�Ɖ��B���̓����ꏏ�Ɏʐ^���B��q�ǂ��E�E�E��l�܂ł�����B �T���^�����h���_�́A�X����葺�i���݂͐[�Y���j���T���^�N���[�X�̂ӂ邳�Ƃł���t�B�������h�����k�A�S�Ǝo���s�s�̒����������̂��@�Ɍv��E���݂��ꂽ�B ���H��\��Ήw���������B ���ꂩ��A��x�͏���Ă݂����Ǝv���Ă����ܔ\���ɏ�Ԃ���B �V�D�@�@�X�@�A
�\��Ήw�֒������B �w�̔��X���̂����Ă݂��B�y�n�̂��̂͂Ȃ�������H �܋l�߂ɂ����R�������ɐ����Ă���B�R�̑������̒n��́A�����ƎR�̕�ɂɈႢ�Ȃ��B �ڂ�ȁA�M���E�W���j���j�N�A�R�킳�сA���ǁA�����݁A�����݁A����̂߁E�E�E�E�E �������R�������B�V�N�ň����B1��150�`250�~�B �߂��ɏZ�݁A�����A���̂ł���A�����������~�������̂���ł���B �u�ڂ�ȁv�́A���邱�ƁA���܂������Ƃ����߂Ăł���B �����̍D��S���ق�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�����Ă݂����Ȃ����B������A�����邱�Ƃ͏��m�̂����ł���B�u�ڂ�ȁv�͐���Ƃ��~�����B�M���E�W���j���j�N�A�R�킳�т������Ă��܂����B�V�����ɂ����ł�������B �w�̃z�[���ɁA���]�[�g���_�?��Ґ��������Ă����B �y���݂ɂ��Ă����ܔ\���ɏ�Ԃ���B����Ă݂������[�J�����Ƃ��ēS���t�@���������B �ܔ\���͑S��147.2�L���B�H�c���E���\��w�ƐX���E�암�w�����ԘH���ł���B�C�ƎR�A�Ìy����̎���ӂ��i�F���y���߂�B �ܔ\���͓S���ʐ^�B�e�|�C���g�Ƃ��Ă��m����B�C�ݐ����肬��ɑ����Ԃ�A�Y��Ȋ�؎R���o�b�N�ɑ�����i���B�e����Ă���B��i�|�C���g�͏��s�^�]���Ă����B�[�z���C���ł́A�[�z�̃r���[�|�C���g������B���{�C�ɒ��ޗ[�z��������Ƃ������A���Ԃ̎��ԑтŎc�O�ł������B�ό���Ԃ̂��ꂵ���T�[�r�X�ł���B �u����~�v�ł�10����Ԃ����B��Ԃ��~��Ċ��܂ōs���Ă݂��B �u���{�̗[�i�S�I�v�ɔF�肳��Ă������~�́A�����S�N�i1792�j�̒n�k�ɂ��ł�����l�B���̐́A�a�l�����̏��~�������������Ƃ������I���L��ɑ����Ă���B ���Ɣg���Ԃ������{�C�Ɏ������Ă���B���Ɏ��̕��w��������Ă���B �ԓ��C�x���g���s���Ă���B ������w�`���쌴�w�ԂŁu�Ìy�O�����̐����t�v���������B����2�l�̑t�҂ł���B�����̗͋������t�A�S��h���Ԃ�Ìy�O�����B�Ìy�̌i�F�߂Ȃ��璮�����Ƃ��o�����B�W�]���E���W(�擪���)�ʼn��t���Ďԓ��Ƀ}�C�N�ŗ����Ă���B�Ìy�٢���ף���������������ԓ��ł͕������Ȃ������B�悭������ɂ��������Ɏ������ƐX����������B �i�q�����[�J���F�������ꂽ�����Ís���Ă���B�Ԓ����ω��������Ċy�����B ����̊�؎R���ԑ����猩����B��Ԃ���ł͂悢���͂Ȃ��Ȃ��������Ȃ��B �암�w�Ői�s�������ς���čO�O���������B �@�@�y�O�@�O�@���@���z
�O�O�w�ɒ����ƃo�X���������Ă����B���ꂩ��O�O�����̍������ł���B �l�o�������B�����a�Ɋ������܂ꂽ�B�x�����̕����̍������J�Ő��ʂɉf���Ĕ������B������t�̂�������֓��ꂵ�����I �O�O�͒Ìy10���̏鉺���B�������w�̍��̖����Ƃ��Ēm����O�O�邪�V���{���B3�w�̓V��t�̔��������ǂ���Ո�т̌����̌i�ϔ����������Ă�B�t��2600�{�̍����炫����颍O�O���܂裁A�������̎��ł���B 5���߂��Ȃ�A�z�������Ȃ��Ă����B�}���Ō�����ڎw�����B�ڂɉf����͍̂��̃I���p���[�h�ł���B���w�ɍ炭���͕������B���{�̏t�ł���B�L���������͍��Ə��̐F�����a���Ă���B��������ƃ\���C���V�m�����荬�����č���ࣖ��ł���B�������x�̐��������ƂȂ��ĉf���Ă���B�Ԑ���������Ă�����Ɗ����I�ɁI �W�]�䂩��̊�؎R�����ꂢ�ƕ����ė����Ă݂��B�[�z�ŋt���ł��������ʐ^���B�����B���m�g�[���̎ʐ^�͗]�C�������āA�������đz����~�����Ă���B���C�ɓ���̎ʐ^�ɏo���オ�����B ��̊ۂ����w���鎞��(5���܂łɓ���)���Ȃ��c�O�B��������������B ������ꂩ����A��H����̏h�ł��铒������ցB�O�O����1���Ԕ����炢�v����Ƃ����B �Â��Ȃ�ƌi�F�������Ȃ��̂ł��x�݃^�C���ƂȂ����B �X���͂�̎Y�n�Ƃ��Ēm���Ă���B���S�̂��Y�n�Ǝv���Ă����B�K�C�h�̘b�ł́g��̎Y�n�͒Ìy�n�����Ƃ����A�암�n���ł͖w�Ǎ���Ă��Ȃ��h�ƕ����āA�ӊO�Ȋ����������B���̔F���s���H�@�u�킯�v���������B �X���́A�]�ˎ���A�Ìy�˂Ɠ암�˂ɕ����ꕶ�����y�ɂ��Ⴂ���������B �C��ɂ��Ă͉Ă��Z���~����������^�ɑ����Ă���A�Ìy�n���i���{�C���j�Ɠ암�n���i�����m���j�ł͂������ȈႢ������B ���ɑ����m���ɐ����ΐ����i��܂��j�̂��߁A�ቷ�Ə��J���Â���Q�ɂ݂܂���₷���Ȃ邱�Ƃ���A�_�Y���̕��z�ł͓��{�C���̐�����ɑ��A�����m���ł͍��ؗށi�Ȃ������A�ɂ�ɂ��j���嗬�ƂȂ��Ă���B�u��܂��v�ɂ��Ă͎Љ�ȂŏK���Ă���B ������Ȃǂ��Ă�����A����̏h�E��������(������)�́u�P�̓��z�e���v�ɓ��������B�@�@�@���� �W�D�@�@�X�@�B ���͓�������̃z�e���ɔ��܂����B ���̂͂��߁A�u��������v�̕��������āA�ǂ��ɂ���̂����������Ȃ��A ����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��A�ǂ̕ӂ�ɂ���̂��낤�H�Ǝv�����B �������ƕ����Ă����悻�̏ꏊ��������A�~�̎��X�ŗL���ȂƂ���ł��邱�Ƃ��v���o�����B �������͏H�c���Ɗ�茧�ɂ܂�����A�X���ɂ��߂��ʒu�ɂ���B ���̏h�́A�H�c�����p�s(���Â�)�A����������\�a�c�ɂʂ���r���ɂ���B ���ڊo�߂đ����J���Ă݂�Ǝ��͎͂R����ł���B���R�ɂƂ���ǂ��딒���ۂ�������̂͂����ƍ����낤�H �����̍s�����Z�����B8��40���ɏh���o�������B �H�c��������\�a�c�������B�r���̓����k�J�̂�����͂��̎����ł��c�Ⴊ�[���B�u�i��Ȃ̖������B���ד�(�ʖ�99�Ȃ��蓻)���ď\�a�c�ΌΔȂ֒������B �y�\ �a �c �z
�\�a�c����]�ł����Ԃ̃r���[�|�C���g�E���ׁi�͂����j�W�]��֏オ�����B�̐F�ɖ������Ă����ƌ��n�����B�f���炵�����߂ł���B�����Ȃ��D�V�Ɍb�܂�A�Ζʂ����₩�ŁA���X�Ɛ�����X���Ă���B�����̔��b�c�A��̔������悭������B ����̔��b�c��w�ɂ���\�a�c�A����C�A���ڂ̂悤�Ɍ�����Ζʂ߂Ă���ƌ����̓���Ƃ͕ʐ��E�ł���B �\�a�c�͓�d�J���f���Ŏ���44km�B���[�Q�Vm�œ����^���[�̍����ɕC�G����B�����x��10���[�g���B�H�c���̓c��A�k�C���̎x┌ɂ��łR�Ԗڂ̐[���B �̎��͂́A�����ɂ��A������ɂ��E�E�E�E�ӂ��̂Ƃ����B�k�ɗ��Ă��邱�ƂŊ�����B �\�a�c�̌Ώ�V���D�ɏ��B�H�c���̋x�������D���ĐX�̎q�̌�(��)�܂ł��悻�T�O���ŏ���B�e�[�v�ŗV��������������Ă���B���̐F���ω����āA���Ԃ菼�t�߂͐��F�̂��ꂢ�ȂƂ���ƈē����Ă���B �ΐF���������u���[�F�ł���B��������r�̐F�Ǝ��Ă���B�Ώ�Œނ�����Ă���l�̎p��������B�R�C�A�t�i�A���J�T�M�A�j�W�}�X�Ȃǂ�����Ƃ����B ���̋��܂�����̂��낤����C�̂��ꂢ�ȂƂ���͐��̐F��������������B�S�n�悢�Ώ�V���ł������B �D�����肽�q�̌�����ĎR(���H����)�ԂŖ�14�q�A�������k���������B����͎ԑ�����̒��߂����ł���B���܂��܂Ȑ������Ȃ���u�i�Ȃǂ̍L�t���т̒��𑖂�B�E�ɍ��ɖڂ܂��邵���ꂪ�����B�Ԃ��~�߂Ďʐ^�B�e�A�U�Ă���B���Ă�g�t�����ɕ����Ă݂����Ƃ���ł���B ���̊y���݂̈�ɂ��̓y�n�̋��y����������B ��ɏZ��ł���Ɩk�̐H�ו��ɓ����B ���H�ɂ���ׂ��`���o���B���V�̏�Ɋی^�̔����Ă���ׂ�������Ă���B��ɉ����Ă���A����ׂ����������ē���Ă��������ƌ����B �痿���ɂ���ׂ�������H�ςȊ��������������̒n���̗����ł���B���肽��ۓ�̂��肽��ۂ�����ׂ��ɑ������Ǝv���悢�B�X�[�v�ɂ����Ɨn���ĂƂ��Ƃ����H���ł���B���������܂��Ĕ��������B �`�o�X�̒��ŃK�C�h����ɕ������Ìy�ف` �̂̕����ł��ƃq���g�������������������Ȃ������B �������́u�Ƃ��䂳��͎Ԓ����̉Q�I �����܂��i���܂��j�E�E�E�C���������� ���Ƃ��E�E�E���� �ւ��傱�E�E�E�ւ� �����傱����E�E�E������������ �����ǁE�E�E������ �Ƃ��䂳�E�E�E�ǂ��ɍs���̓��� ���̗��Ō�̍�������\�a�c�s�������B �y�� �X ���z
�\�a�c�s�͋��\�a�c�s�Ƌ��\�a�c�Β��̍����ɂ�蕽��17�N�P���P���ɒa�����Ă���B �����X�ʂ�͈��̂Łu��X���v�ƌĂ�s���e���̓��Łu���{�̓�100�I�v�ɑI��Ă���B�ʂ�͍���F�ɐ��܂��Ă���B ����1km�̓���500�{�̍����������B���������ɉ������k�����C���[�W�������̗����A���܂��܂Ȕn�̃I�u�W�F���z�u����A�����ۗ������đs��ȊG��̂悤�Ȕ��������B���C�g�A�b�v���ꂽ������������Ƃ����B ���̓������J�̍��̒��A�l�o�������A�������͉Ԍ��̉��œ�����Ă���B �S���ɍ��̖����͑������m���Ă��Ȃ��Ƃ���������B��X���������ł��낤�B�K���@��Ɍb�܂�A����̓c�A�[�ł悩�����B�����X�̒ʂ�ɖ��J�̍����ʂ��Y���Ă���B�D�������ł���B ���k�̍������ł�2��3���̗����I���B��H���ˉw�ցB 16�F05���A�V�����͂��4���ɏ���ċA���̓r�ւ����B �X�D�@�܁@�Ɓ@�� ��ɏZ��ł���ƁA�k�̒n�ɂ͒m��Ȃ����Ƃ����肻���ŁA����̋C���������B ����̗��ł��A�������Ƃ��҂��Ă������Ȃ���Ȋ��Ҋ����������B ��������S�[���f���E�C�[�N�ɓ��k�̍������ɍs���Ȃ��H�ƗU�����������B�����s�������Ƃ̂Ȃ����k�n���ł���B�����ɔ�т����B�������ĂQ�l�̖��Ƃ̂R�l�������������B ���߂Ă̓��k�́A������́A�H�ׂ���́A�������ƁA���ׂĂ��������A�V�N�ɉf�����B �Z�����Ԃł��������A����Ȃ�ɁA���R�A�C��A���y�A�����̈Ⴂ�������邱�Ƃ��o�����B ���M���邱�Ƃ� �s����X�V��Ɍb�܂ꂽ�B�C�����������Ƃ��قǕς��Ȃ������B���̔N�X�ŊJ�Ԏ������Ⴂ�A�C�܂���J�Ԃ̍��ł���B�p�فA��H����(�H�c)�A�O�O�A��X��(�\�a�c)�̂���������J�̍���ࣖ��ł������B���J�����ƃs�^���ƈ�v�����B�K�^�ł������B ���k�̍��̖����̖{���͔��[����Ȃ��B�����Ƃ��납��̒��߂͍��̂��イ�����~���l�߂��悤�ɍL���肪����B�W���F���A�X�P�[���̑傫���Ɉ��|���ꂽ�B�Ԃ̐F�ƍ���ɗU���Ă��̏�ɉ������V�����ł݂����B�k���̓~�͊��������B�����ɑς��t��҂��Ĉ�C�ɊJ�Ԃ������̖́A��࣍��ȉԂ�������܂Ƃ��l���䂫����B�k�̍��̍��������Ղ�Ɩ��i�����B �c�A�[���s�͂�������ł�����茩�鎞�Ԃ��Ȃ��B�����ł͂������Ȃ��Ƃ��낾�����͑҂������Ȃ��B���������炢�`�����X�������Ă��邩������Ȃ��B �m��Ȃ��y�n�́A�c�A�[���s���L���ԗ�����Ă��āA�A�E�g���C����m��ɂ͂����Ă����ł���B�\�K���ł����悤�Ȃ��̂ł���Ǝv���悢�B�����Ƃ������茩�����Ƃ���́A����Ɏ����Ōv�悷��悢�B���k�͖��͂���Ƃ���ł���B���̃V�[�Y���ɁA�Ⴄ�ꏊ���K�˂Ă݂����B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















































































